すっかり遅くなってしまいましたが、2018年10月27日(土)に開催された「第11回ダム愛好家との集い in 長良川河口堰&船頭平閘門」についてレポートをお送りしたいと思います。
今回はダムではなく河口堰であったことや、恐らく通常の見学会のコースと同じだろうと想定されたためか、参加者数は13名と少なめでした。
集合
天気予報は前日ぐらいまではずっと雨の予報だったのですが、当日朝には10時ぐらいから晴れる予報になり、集合時間前には奇跡的に雨が上がりました。きっと皆さんの思いが通じたのでしょう。
ちなみに機械設備の解説担当の方は、第1回ダム愛好家との集いで阿木川ダムの機械を担当されていた方でした。何年かやってるとそういうこともあるんですね。

管理所内見学
駐車場での挨拶が終わり、続いて管理所内へ移動します。玄関にはPOPが掲示されていました。こういうの、結構うれしいです。
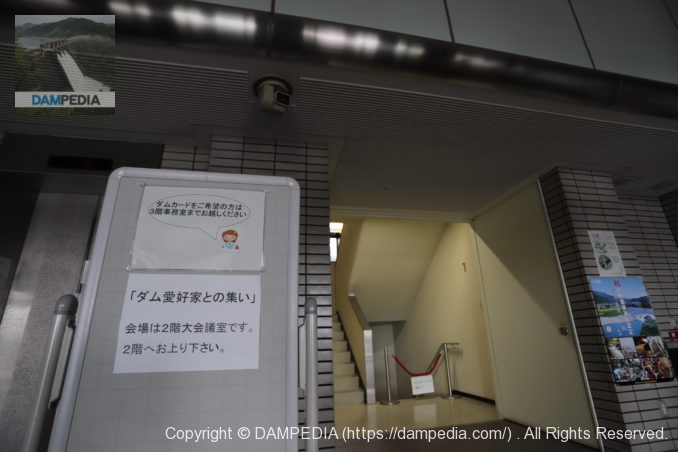
会議室にて長良川河口堰概要説明
管理所の中に入り、すぐに会議室に移動します。ここで長良川河口堰について概要説明を聞きます。

その後、操作室に移動し色々と説明を受けます。残念ながら写真撮影が禁止されているため写真はありません。
ちなみに右岸に設置されている閘門の操作も操作室から遠隔で行うそうです。
また、この時に津波の際のゲート操作がどうなるのか伺いましたが、全開になるんだそうです。排水機場では全閉すると聞いていたので、まったく真逆で驚きました。津波でゲートが破損して動作できなくなるリスクの方が大きいのでしょう。
ゲート巻上げ機室見学
続いて左岸の魚道を見学しゲート巻上げ機室を見学します。皆さん真面目に説明を聞いていました。

…と、これにて長良川河口堰での見学は終了。監査廊もないのであっさりです。本当は巡視船に乗って閘門体験をしていただきたかったのですが、乗り場が出水のため破損してしまったらしく、残念ながらコースに含めることができませんでした。また機会があれば長良川河口堰での閘門体験をしてみたいですね。
午後は木曽川観光船に乗船
午後は希望者のみ木曽川観光船に乗船して、船頭平閘門を体験します。まずは集合場所の葛木港。ここで乗船します。

木曽川のケレップ水制
ちょっとした舟遊びですね。お弁当を食べながら移動しますが、風が強くてお弁当の写真を撮ってる余裕はありませんでした😁
葛木港を出港したボートは、まず木曽川を下ります。途中、明治時代のオランダ人技師デ・レーケによるケレップ水制をボート上から見ることができます。(土木学会選奨土木遺産)

船頭平閘門 木曽川側閘門扉
木曽川を南下して船頭平閘門が見えてきました。「閘門」とは水位がそれぞれで違う河川を船舶が航行する際に、水門で水位を調節して行き来できるようにする設備のことをいいます。船頭平閘門では木曽川と長良川を行き来できるようにしています。ちなみに国の重要文化財に指定されています。

船頭平閘門の木曽川側閘門扉開放
木曽川側の閘門扉が開きます。ちなみに開けてもらうには写真では見えていませんが右側にベルがあり、それを引っ張って鳴らすと作業員の方が出てきて開けてくれます。

閘室内の給水の様子
閘室内に船を移動させます。この日は木曽川が長良川よりも水位が低い状況でしたので、木曽川側の水門を閉じて閘室内に水を給水。水位を長良川に合わせます。給水中は写真のようにブクブクと泡が出てきます。

船頭平閘門の長良川側閘門扉
長良川をしばらく航行したのち、再び船頭平閘門に戻ります。下船して船頭平河川公園を散策するため長良川側に船を係留します。

治水の恩人ヨハネス・デ・レーケ像
明治治水の三川分流工事の功労者であるオランダ人技師ヨハネス・デ・レーケを讃えるための銅像が公園内に建てられています。

国土交通省船頭平閘門管理所 木曽川文庫
木曽川文庫内に入って解説を聴きつつ見学します。ここには宝暦治水や明治治水に関する文献や資料などが豊富にあり、木曽三川の苦難の歴史をうかがい知ることができます。

船頭平閘門の閘室
長良川側の閘門はその上が橋になっていて、閘室内を俯瞰で見ることができます。

船頭平閘門のベルを鳴らす
再び乗船し、今度は長良川側の門を開けてもらうためにベルを鳴らします。その大役に私が務めさせていただきました。貴重な体験なので、もし閘門を通過する機会があったら鳴らさせてもらいましょう。

船頭平閘門の閘頭部
今度は水位が高い状態にありますので、閘室内の水を排水して水位を下げて木曽川の水位に合わせます。そして通過。レンガ積みの扉室ですが、明治の建設当時のままだそうです。角の船が衝突する可能性のある部分は、レンガではなく花崗岩にして耐久性をアップさせています。

船頭平閘門通過後は葛木港に戻り、本日の行程はすべて完了となり解散となりました。
今回はメインがダムではありませんでしたが、木曽三川の治水の歴史を知るいい機会だったかと思います。また、こうしたダム愛好家との集いも一風変わって良かったように思います。ぜひまた次回第12回ダム愛好家との集いでお会いしましょう!




コメント